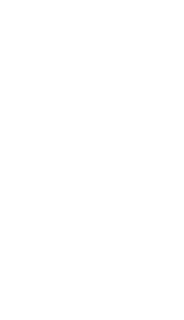私はせっかちです。人と話している時も相手の言葉をさえぎって自分で結論を言おうとします。よく女房から「あなたもお坊さんなんだから、少しは相手の話を聞いたら」と叱られます。
反対に、仏様はじっくり相手の話を聞く方でした。お経の中に仏様の話を聞こうと集まっている人々に対して、仏様は長い時間瞑想するだけで一言も言葉を発せられなかったそうです。しびれをきらした5000人のお弟子がその場を去っていったとか。仏様はそれを止めようとしませんでした。おそらくは、「待つことを知らぬ者には、仏の教えの深い意味を悟ることは出来まい。」とお思いになったからでしょう。
忠臣蔵で有名な播州赤穂の城代家老の大石内蔵助に、こんなエピソードがあります。ある日のことでした。なんとかして町おこしをしたいと思った城下の人たちが、「塩を作ってみてはどうだろう」と考え、ご家老さまに進言しました。これを聞いた内蔵助は、「なかなか善き考えではある。追って沙汰を出すから、しばらくの間待つように」と答えたのです。ところが半年経っても、1年待ってもなんの沙汰もありません。月日はどんどん過ぎていきました。「ご家老さまは調子のいい事をおっしゃったけど、私たちのいうことなんてお取り上げになる気持ちはなかったに違いない」とみんなは諦めてしまいました。そして13年が経った時、突然、お城から呼び出しがかかったのです。「みなの者、待たせたな。塩を作ることを許可いたす。」そういう内蔵助の言葉を聞いて、みんなびっくりしました。「なにを今さら」と思ったからです。そんなみんなを諭すように内蔵助はいいました。「よいか、塩を煮るには薪がいる。薪のためには森がいる。そなた達の考えを聞いた時、わしは植林の計画を立てた。この計画なくしては、山は丸はだかになり自然は破壊される。決して、目の前の欲だけに心を奪われてはなるまいぞ。待つことを知らぬ者には大事を成し遂げることは出来ぬ」と。
昼行灯と陰口をたたかれながらも、時の来るのを待っていた内蔵助には、仏様の教えが分かっていたのかもしれませんね。