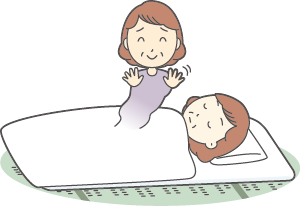心臓の動きが止まると、私たちの人生はストップします。
お医者さんが手を取って脈拍を看て、それからまぶたを開いて瞳孔の反応を調べるのをご覧になったことがあるでしょう。そしてまぶたを閉じさせると静かに「ご臨終です」と告げ、死者に敬意を表して頭を下げる時、私たちはなんともいえない厳粛な気持ちになってしまうものです。
生・老・病・死は、私たちにとって避けることの出来ない苦しみであるとお釈迦さまはお説きになっています。それだけに、最後の苦しみである死を迎えた人に対して、私たちは思わず手を合わせたくなるのでしょう。
お医者さんと違ってお坊さんの場合、亡くなった人の人生がストップした時から出番がやって来ます。家族の人から「枕経をお願いします」との連絡を受け馳せ参じるのですが、その場合、よく言われるのが「死に顔を見てやって下さい」という言葉です。もちろん、私もそれはお坊さんの務めと思っていますが、顔に覆われた白い布を取るまでは「どんなお顔だろう」と胸がドキドキするのです。そしてその顔が安らかである時、心底ほっとします。それは、この人も納得してあの世に旅立ってくれたのではないかと思えるからです。
そんな時、家族の人から「これで本人も楽になったんでしょうね」と問いかけられると、「私もそう思います」と答えてお経をあげさせてもらうのです。
私は死ぬことをストップだと表現しましたが、実は亡くなった人の遺体を前にしてお経をあげ始めると、お坊さんの仕事は、ストップの赤信号から、ゴーの青信号を出すことではないのだろうかと考えてしまいました。
それというのは、自分自身もガンになったノンフィクション作家の柳田邦男さんの講演を思い出したからです。柳田さんは、こう訴えました。「人は物事を見つめる時、どんな立場に立って判断するのでしょうか。死という人生の終着駅についた人には三つの立場があります。一つは一人称の死。これは自分自身の死です。二つには、二人称の死。これは愛する家族が死者を思う立場です。そしてもう一つは三人称の死。死ぬのはごく当たり前という第三者の目です。お医者さんの目は、この三人称の死にあるのかもしれません。でも、私はせめて二・五人称の目を持ってほしいと願います」と。
そう話していた柳田さんの言葉から、私は死を終わりと受けとめたくない宗教的な願いを感じとらずにはいられなかったのです。