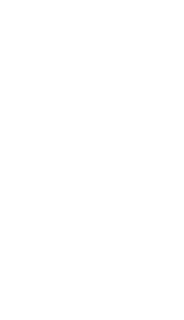それまで気にもしていなかったことが、あるきっかけで、大きく眼を開かされるということがあるものです。
お盆が過ぎ、やれやれと、ほっと一息ついた時のことでした。突然、ひどい腰の痛みに見舞われました。あまりの痛さに身動きすることが出来ず、ほとんど寝たきりという状態。3週間ほど病院に通ったのですが、あの時ほど、手すりや杖をありがたいものだと思ったことはありません。
それまでは、坂を登るにしろ、階段を上がるにしろ、「こんなもの」と気にもしなかったものが、とても大切なものだと肌身で思い知らされました。それまでは、檀家さんのお家にお参りにいっても、廊下のあちこちに手すりがあるのを眼にして、みっともない、格好が悪いと思っていた私です。「ごめんなさい」、謝ります。お年寄りにとって、それは、本当に必要なものだったんですね。
幸い、今は、それに頼らなくても、歩けるまでに回復しましたが、私もだんだんに年をとっていきます。いつの日か、本当にそれが必要となる日も来るでしょう。
そう反省していると、家内が「そんな殊勝な気持ちが、いつまで続くのかしら」と皮肉をいいました。ムカっと来て、「なに!」というと、「あなたは、日頃から姿勢が悪いのよ。姿勢が悪いから腰に無理が来るのよ」と判決を下すような言葉が返って来ました。
ご存知のように、腰という漢字は、お月さまの月という字に要という字の組み合わせで出来ています。この月は、月日の月ではありません。身体についている肉という字が変形した字で、「肉づき」といいます。メタボといわれるほど肉づきのいい私です。だから正座が苦手なのですが、背筋を伸ばし、ちゃんとした姿勢で坐ることが腰には必要なことだと健康管理の本には書いてあるのだそうです。そして、「静かに呼吸を整えることが身体にも心にもいいそうよ」と家内は説明しました。
そういえば、お釈迦さまがお悟りを開かれたお姿は、私たち日本人のような正座はなさっていないものの、背筋をちゃんと伸ばされています。胡坐を組んでいるように見えますが、あのお姿は結跏趺坐(けっかふざ)といって、ちゃんとした瞑想の作法なのです。足の短い私には両足の足の甲を、それぞれの足のももの上にのせるこの坐り方は、とても出来ませんが、せめて背筋を伸ばすという姿勢は心がけようと、心に決めました。それでなければ、家内をはじめ、まわりの人からも腰くだけといわれかねません。
蛇足ながら、要という字に女という字があるのは、昔から腰の坐っているのは女の人だったからなのだそうです。